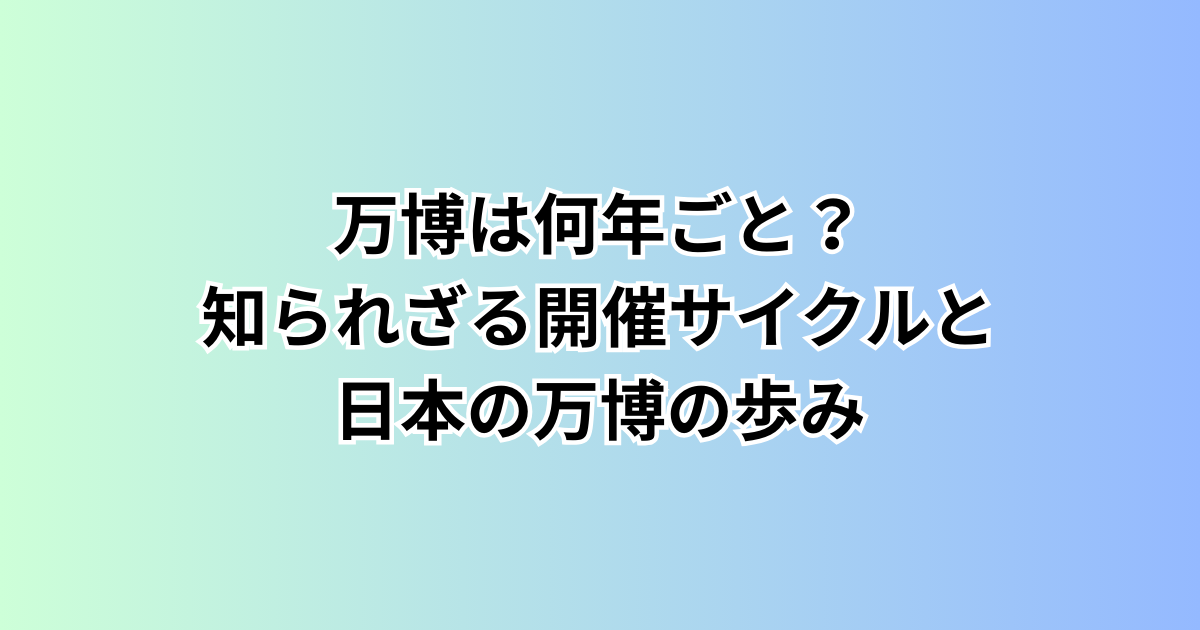「万博って何年ごとに開催されてるの?」
ふとニュースで話題になる万博。2025年には大阪・関西での開催が予定されていますが、そもそもこの「万国博覧会(万博)」とは何なのか、どれくらいの頻度で開かれているのか、意外と知らない人も多いのではないでしょうか。
この記事では、万博は何年ごとに開催されるのかという基本から、これまでの日本の万博の歴史、そして次回の開催地である大阪・関西万博の注目ポイントまで、初心者にもわかりやすく解説していきます。
目次
万博は何年に一回ある?
引用元: 月刊不動産 | 公益社団法人 全日本不動産協会
万博は何年ごとに開催されるのか? そんな疑問に答えながら、その背景と意味をわかりやすく解説します。
万博は基本的に「5年ごと」に開催されることが原則です。これは、登録博(通称:本万博)という正式な国際博覧会のルールで、BIE(博覧会国際事務局)によって定められています。また、その合間に小規模な認定博(スペシャライズド万博)も開催されることがあります。
5年というスパンは、単に時間を置くためではなく、開催国がしっかりと準備を整えるために必要な期間でもあります。開催国はその期間中にテーマの策定、会場の建設、参加国との調整など、多岐にわたる準備作業を行います。準備期間が長いほど、テーマや展示の質も高くなる傾向にあります。特に、最近の万博はSDGsやAI、ロボティクスなど、社会課題と直結した内容が多く、単なるお祭り的イベントではなく、国際的な知見を持ち寄る場へと進化しています。
確かに、あれほど大規模なイベントを成功させるには、時間的余裕と丁寧な設計が欠かせません。何千万人もの来場者を想定し、インフラの整備、安全対策、バリアフリー対応など、細かな部分まで配慮が必要です。逆に、短期間で準備を進めれば、それだけリスクやトラブルも増えてしまうため、5年という期間は理にかなった設定だといえるでしょう。
万博開催に必要な準備要素の一例:
- テーマの決定と各国への周知
- 会場のインフラ整備と都市計画
- 交通・宿泊施設の充実
- 安全対策とセキュリティ管理
- バリアフリー・ユニバーサルデザインの導入
日本では何回万博が開かれた?
日本ではこれまでに6回の万博が開催されています。
- 1970年 大阪万博
- 1975年 沖縄国際海洋博覧会
- 1985年 筑波科学万博
- 1990年 花と緑の博覧会(大阪)
- 2005年 愛・地球博(愛知)
- 2025年 大阪・関西万博
中でも1970年の大阪万博は、アジアで初めての大規模万博として歴史的な転機でした。「人類の進歩と調和」を掲げ、月の石の展示が象徴的でしたね。当時の空気感や、人々の期待と熱気が今も語り継がれています。経済成長の真っただ中だった日本にとって、この万博はまさに国の自信と誇りを形にする機会だったともいえるでしょう。
引用元:オフィシャルサイト(大阪府日本万国博覧会記念公園事務所)
また、2005年の愛・地球博では「自然の叡智」というテーマが掲げられ、地球環境問題に対する意識を高めるきっかけとなりました。このように、日本で開催された万博は、それぞれの時代背景と社会課題を色濃く反映していることがわかります。
万博去年開催地
前回の万博開催地がどこだったのかを知ることで、今後の万博の流れが見えてきます。
直近で開催されたのは2020年予定だったドバイ万博です。ただし、パンデミックの影響で2021年〜2022年に延期されました。テーマは「心をつなぎ、未来を創る」。このドバイ万博は中東初の開催で、グローバルな団結の象徴として多くの話題を集めました。
引用元:空間デザイン・建築メディア
ドバイ万博の特徴:
- 世界192カ国が参加
- 持続可能性・モビリティ・機会の3つのサブテーマ
- 完全予約制による来場者管理
- オンライン配信やデジタルパビリオンの導入
この形式は、今後の万博運営の新たなスタンダードになる可能性を示しました。人の移動が制限される時代においても、技術の力でつながり、共有し、理解し合える万博の在り方を提案した点は、非常に革新的でした。
万博何年ごとに開かれる?その背景と意味
万博とは?
万博、すなわち国際博覧会は、国際的な文化・技術交流の場です。各国がそれぞれのアイデア、発明、文化を紹介し、未来に向けた社会の姿を提示するという大きな意義を持ちます。
時代ごとにテーマは変わりますが、常に「未来」や「人類の課題」がキーワードになります。まさに、世界が一堂に会し、新たな道を模索する場所なんです。
また、万博は「文明の鏡」とも言われます。開催される時代ごとの問題意識や価値観が反映され、今、世界が何を重要視しているかが明確になります。技術革新や社会変革が急速に進む現代において、こうした国際的な対話の場は非常に貴重です。
万博の目的と意義
万博は一見、巨大な展示会のようですが、その中身はとても深い。目的は技術革新の紹介だけでなく、国際協調や文化交流、教育的な啓発も含まれています。
過去には、動く歩道や携帯電話の原型など、今では当たり前の技術が初めて紹介されたのも万博でした。未来を先取りする場所、それが万博の最大の魅力のひとつでしょう。
万博はまた、国際的な文化理解を深めるための橋渡しとしても機能します。世界中の人々が、文化や思想、価値観を共有することで、新たな気づきや理解が生まれます。それが、持続可能な世界を築くための第一歩となるのです。
万博の開催プロセス
万博の開催地は、BIEによる加盟国の投票で決定されます。そのため、単なるイベントではなく、国際政治や経済の思惑も絡む、かなりシビアな選考が行われています。
開催を希望する都市は、テーマの提案から運営体制、経済的支援、国際協力体制の有無など、多角的な審査を受けます。その後、各国の代表による投票を経て、最終的に開催地が選ばれるのです。このプロセスは、国際的な公平性と透明性を保つために欠かせない仕組みとなっています。
2025年の大阪・関西万博も、激しい誘致合戦を勝ち抜いての開催です。選ばれたからには、それにふさわしい内容が求められるわけで、その責任の重さは想像以上です。国内の民間企業や大学、自治体の連携が鍵となり、まさに「オールジャパン」での取り組みが進められています。
今後の万博に期待されること
今後の万博では、SDGsやSociety 5.0のような地球規模のテーマが主流になると予想されます。ただ見て楽しむだけでなく、参加者自身が未来の社会づくりに関与する、そんな“共創型万博”が新しいスタンダードになっていくでしょう。
2025年の大阪・関西万博も、その方向性を強く打ち出しており、「展示を見る」から「未来を体験する」場としての進化が注目されています。教育機関との連携による学びの場や、来場者が課題解決に参加するプログラムなど、実践的かつ参加型の仕組みが多数用意される予定です。
また、今後の万博では環境負荷の少ない設計や運営、デジタル活用による効率化なども大きなテーマです。持続可能性が問われる現代において、「万博そのものが持続可能であること」も問われる時代が来ています。
まとめ
万博は単なる展示イベントではなく、国際社会が未来を共に考える場です。
「万博は何年ごと?」という疑問に対しては、基本的に5年に一度というルールがあり、その間に各国が準備を重ね、時代を反映したテーマを通じて世界へ発信しています。
日本ではこれまでに6回の万博が開催され、それぞれが時代の象徴として多くの人々に影響を与えてきました。2025年には再び大阪で開催される予定で、次世代の社会課題にどう取り組んでいくか、世界中が注目しています。
今後の万博は、参加する・共創する時代へと変化し、ただの「見るイベント」ではなく、未来社会をつくるための実験場となっていくでしょう。