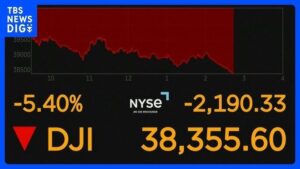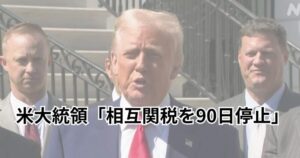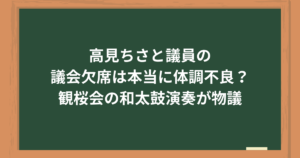またしても政府は国民を苦しめる決定を下した。厚生年金保険料の増税が決定し、高所得者をターゲットにした負担増が進められている。しかし、これは本当に公平な制度改革なのか?政治家や官僚たちは自分たちの特権を守りながら、庶民にばかり負担を押し付けているのが現実だ。年金制度を維持すると言いながら、その実態は“取り立て”ばかりで、国民が得る恩恵はどんどん削られていく。国民の怒りを無視したこの暴挙に対し、今こそ声を上げるべきではないのか?本記事では、厚生年金保険料増税の実態と、それがもたらす問題点を徹底的に暴いていく。
厚生年金保険料の増税内容
2027年9月から標準報酬月額の上限が引き上げられ、高所得者の負担が増加する。
政府の増税理由と問題点
年金財政の安定化を名目にしているが、政治家の無駄遣い削減が先ではないかとの批判がある。
現役世代の経済的負担
月1万〜3万円の負担増が家計を圧迫し、特に都市部の生活者や子育て世代に深刻な影響を与える。
政治家の優遇と庶民の負担
政治家の年金制度は手厚く守られているのに対し、庶民にはさらなる負担が押し付けられている。
目次
厚生年金保険料更に増税へ!またしても庶民いじめの増税策

年収798万円以上がターゲット
政治家たちは「高所得者なら払えるだろう」と軽々しく決めているが、彼ら自身の年金負担はどうなっているのか?国民には増税を強いる一方で、自分たちは優遇年金をしっかり確保しているのが現実だ。 厚生労働省は、2027年9月を目途に、年収798万円以上の会社員に対して厚生年金保険料の上限を引き上げる方針を示している。現在の保険料上限65万円を75万円〜98万円に拡大する案が検討されており、これにより、月額1万円から3万円の負担増が見込まれる。
受給額の増加は本当に恩恵か?
「負担が増えるが、その分将来の年金額も増える」と政府は言うが、果たして信用できるだろうか?過去にも年金改革と称した変更が行われたが、結局は支給開始年齢の引き上げや給付額の減額が繰り返されている。今回の増税も、本当に将来の受給額増加につながるのか、極めて疑わしい。
年金財政の安定化という名の言い訳
政府は年金財政の安定化を口実に増税を正当化しているが、その前にやるべきことがあるだろう。まずは無駄な支出を削減し、議員特権を廃止し、官僚の天下りを根絶するべきではないのか?無駄遣いを放置したまま、国民から巻き上げることしか考えていない政治家たちに、年金制度を語る資格などない。
厚生年金保険料更に増税へ!現役世代の負担が限界に
手取り収入の大幅減少
高所得者層にとって、毎月の負担が1万〜3万円増えることは、可処分所得の減少につながる。特に都市部で生活する家庭では、家賃や教育費などの固定費が多く、今回の負担増は生活水準を大きく引き下げる要因となる。政治家は、この影響を全く理解していないのではないか?
在職老齢年金の「見直し」=ただの帳尻合わせ
2026年4月から、在職老齢年金制度の基準額が50万円から62万円に引き上げられる予定となっている。これは一見すると高齢者に有利な変更に見えるが、実際は働く高齢者が増えたことによる単なる調整に過ぎない。政府の狙いは、あくまで支給額を抑えることだ。
家計を圧迫する政府の無計画な制度運営
政治家たちは「庶民の生活」などまるで理解していない。彼らは議員宿舎で格安家賃で暮らし、高級料亭での会食に税金を浪費し、何の痛みも感じずに増税を決めている。子育て世代にとって、教育費や住宅ローンなどの出費がかさむ中での負担増は厳しすぎる。政府が本当に国民のための政治をしているなら、まずは自分たちの特権を見直すべきだ。
まとめ
厚生年金保険料の増税は、日本の年金制度を維持するために必要な措置と政府は主張するが、実際は現役世代への新たな負担強制に他ならない。高所得者層を中心にさらなる負担増が求められる中で、制度の公正性や負担と給付のバランスはますます疑問視される。
国民はこのまま政府の言いなりで負担を受け入れ続けるのか?年金制度を維持するために、まずは政治家や官僚が率先して身を削るべきではないのか?今後の政策の動向を注視しながら、国民一人ひとりが声を上げることが求められています。